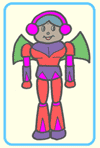Writer:メグ☆ママさん(公開日:2001年3月)
この場を借りてカミングアウトする。
私は『明星』を毎月購入していた。付録だった『YOUNG SONG(ヤンソンと読む)』を片手に、誰よりも早く新曲を覚えたり、みんなが知らないCMソングを全部覚えたりしていた。もちろん本誌の方も隅々まで読んでいた。インタビューにいちいち感化され、「キョンキョンのやってる事ってカッチョエエ」と、ハサミで同じ様にソフトな半刈りの髪型(『なんてったってアイドル』の少し前)にした事もある。
そしてもう少しカミングアウト。『明星』に飽きた頃…たぶんアイドルの中にも作詞や作曲をする人が出て来て、自分の事をアーティストと言い始めた頃、『PATI-PATI』に走った。もちろん毎月購入。こっちは歌本の付録は無かったが、インタビューが濃密だった(12~13才の頭には)。好きなアーティストのルーツを知る事が出来たし、彼らの苦悩やレコーディングの重たい空気を共有出来た。全国に売られている雑誌だっていうのにインタビューを隅々まで読んで、「自分だけがこのアーティストの真実のファンだ」なんて勘違いしていた。
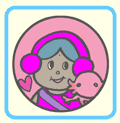
しかしそれも束の間。何やったって結局はテレビに出てヘラヘラしてんじゃんねぇ~と悪態をつき始めた頃、『宝島』を読み始めた。キッカケは、チェッカーズの表紙だった。『PATI-PATI』の延長線上に位 置する雑誌だと、勝手に思い込みページをめくっていた。
この1冊で私のバンド人生が始まったのだ。初めは名前を覚える事に必死だった。何しろテレビに出ているバンドなんて、全く載っていなかったのだから。そのバンドの音を聴いた事も無かった。きっとその頃は「みんなと違う雑誌を読んでるアタシ」に夢中だったのだろう。ワザとらしくインディーズバンドの話をしたり、大江千里や渡辺美里が好きだと言っているミュージシャンの歌を口ずさんだりしていた。
しかし「アタシに夢中」な時期は、すぐに終わった。実際にライブを「おっかけ」るようになったからである。ライブハウスなんてドキドキ!不良って言われちゃう!!…そんな風に頬を紅潮させて観るライブは、本当に格別 だった。そして家と学校だけでは知り得なかった、多くの事を学んだのだ。雑誌を広げてるだけではわからなかった、たくさんの事を。もっと知りたい、もっと関わりたい…そういう思いが芽生えたのと同時に、「スタッフやらない?」と誘われるようになった。
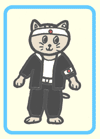
とにかく嬉しい気持ちを押し殺して、スタッフの仕事を覚えた。そつなく仕事をこなせるようになった頃、『平成名物TV イカす!バンド天国』が放送をスタートした。「バンドのスタッフって何すんのよ」と、あまりイイ顔していなかった母は、この番組を眺めては「このコ、カワイイわ」と言うのが楽しみになり、クラスの友達からは「私も行ってみたい~」とせがまれる様になった。本当にあの頃は皆が皆バンドに夢中になった。今までジャニーズ事務所が用意したアイドルで満足してきた女のコ達が、自分達でアイドルを見つけ出す事に夢中になり始めていたのである。
そして女のコ達はイカ天だけでは飽き足らず、ホコ天にも足を運んで好みのバンドを探し出していた。友達に名前を言って、「知らな~い」と言われる事が気持ちよかった。誰よりも早く好きになったという、小学生の恋みたいな優越感だったとしても、とても気分がよかったのだ。たとえみんなが知らないバンドでも、そのメンバーに自分の事を覚えて欲しくて必死だった。普通 はしないだろうと思われるプレゼントをしてみたり、いつも同じ服でライブに行ったり。髪型や小物のトレードマークを決めたりもした。「○○ちゃんって、ちょっと変わってるよね」が、ホメ言葉になっていた。
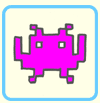
そんな『天・天ブーム』はいよいよ本格的になり、ホコ天とライブハウスは毎日お客さんで溢れていた。イカ天には作家の林真理子や中野翠らが結成した『イカ天ファンクラブ』の会報が、毎週ファックスされていた。在宅審査員と呼ばれる関係者の中には、ミュージシャンも数多く存在するようになった。ラバーソウルやマーチンのおデコ靴は市民権を得て、竹下通 りの丸玉商店には全国から注文が殺到した。いわゆる「バンド好きなコ」がクラスの半分近くを占めるようになり、『宝島』は普通 の雑誌と同様に回し読みされていた。
そして気づくとバンドの数はものすごい事になっていた。中には「デビュ-前にハクをつかせるため」と、事務所に言われてバンド活動してるなんていうのもあった。あらかじめ優勝者が決定しているオーディションがあったり、デビュ-するにあたってボ-カル以外の全員が辞めさせられた…なんて話もチラホラあった。
そんな中でも、やはりイカ天はおもしろかった!ホコ天は刺激的だった!確かにクズみたいなバンドも増えた。しかしそんなヤツらの音は残らない、強靱な耳が出来上がった。自分達で自分達の事を「奇抜で個性的なバンド」と、言い出す輩も出てきた。しかし「それは違うだろう」と言えるようになってた。あだ名しか知らないコがいたり、どこに住んでるのかイマイチ把握できないコもいた。だけど大事なのはそんな事じゃない事を知った。ずっとこのままでいられるワケがないと誰もがわかっていた。わかっていたから私達は大きな声で騒ぎ、ライブハウスにたむろしてたのだ。本当の事より、楽しい事が大事だったのだ。

ブームに翳りが見え出すのはそれからすぐだった。ライブハウスと周辺住民の対立やバンドの解散(理由のほとんどが女絡みというのが残念)、バンドやそれに集まるコ達を商売道具にしか見ない大人が増えた事…。そういった状況の中に身を置いてまで、バンドをおっかけるコはいなかった。
イカ天出身が意外なバンド、ブランキー・ジェット・シティのVo.浅井健一は言った。「音楽はみんなが振り向くんだ。それがどんな音であってもね。だけど、そっぽ向かれるのも早いんだ。バンドブームはそれをイヤっていう程、見せつけたってだけ。バンドが商品にされたからダメになったんじゃない、商品にしかならないバンドだけになったからダメになったんだよ」…そうなのだ。私達は「アイドル」がたくさんいるホコ天が好きなのであって、「商品」が並べられてるホコ天が好きなのでは決してなかった。私達は自然と「商品」と「アイドル」の違いを嗅ぎ分けていたのだ。カタログになってしまったイカ天に飽きるのも、ある意味仕方がない事だったと言えるだろう。
今もパッケージされて売り出されるアイドルが存在する反面 、雑誌の読者モデルやクラブのDJといった、誰のものさしでも測れないアイドルが存在している。見えないモノを求めるほど飢えていない彼らにとって、たった一つの探しモノは「アイドル」だ。そして「アイドル」という言葉は探されるモノとして、これからも存在し続けるのであろうと私は感じている。